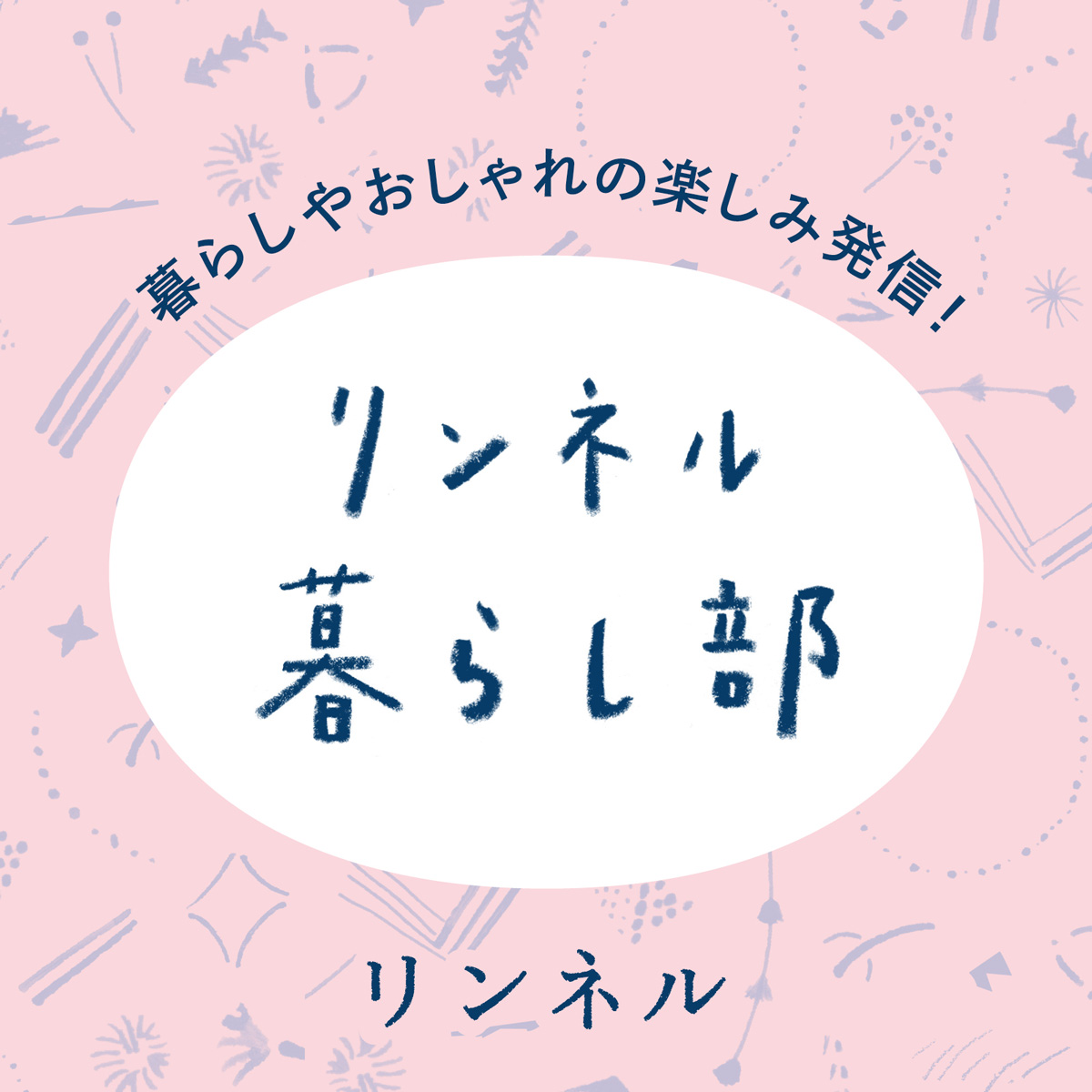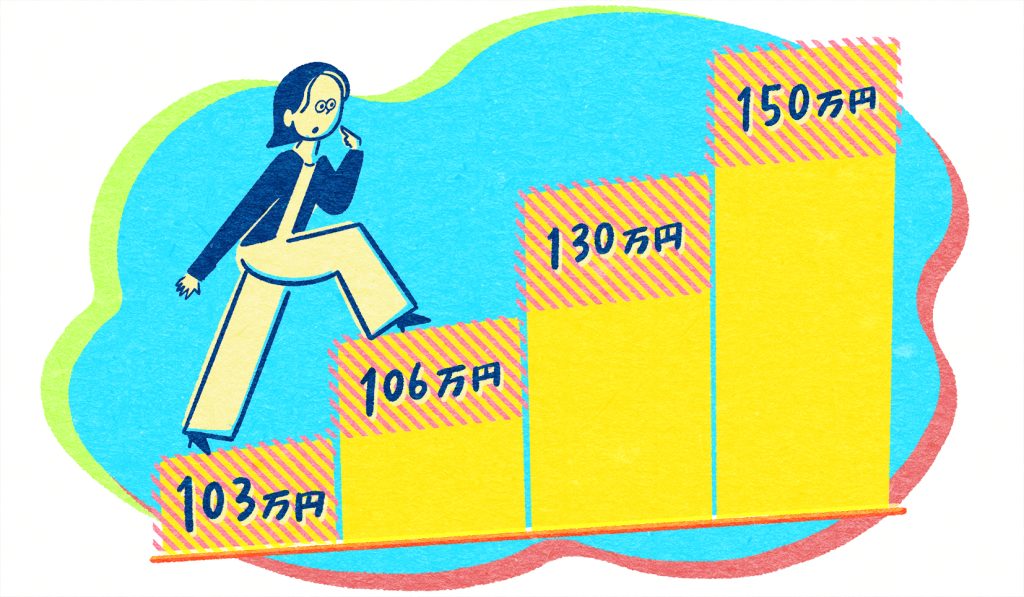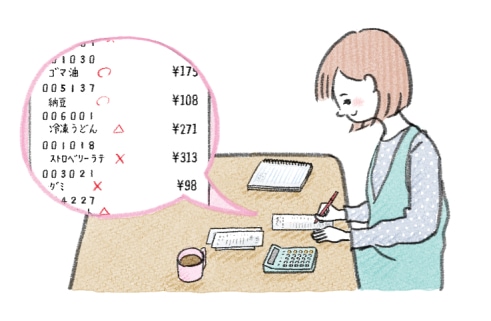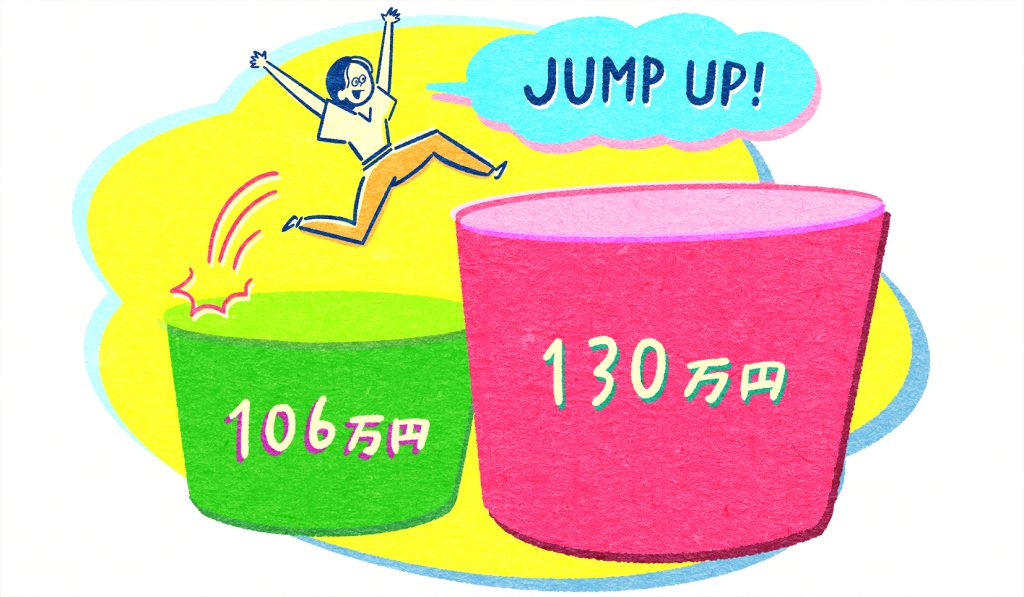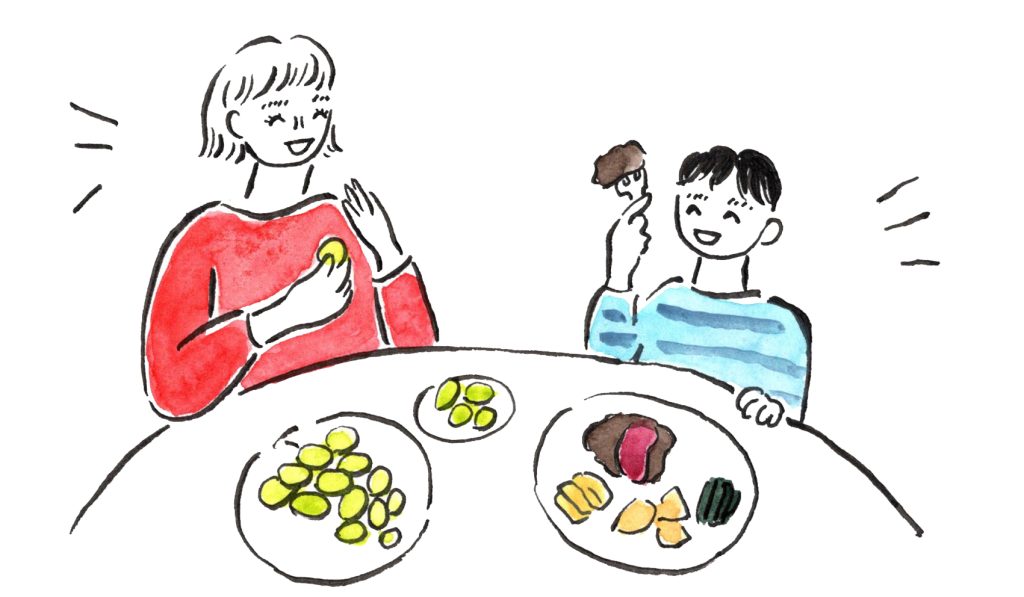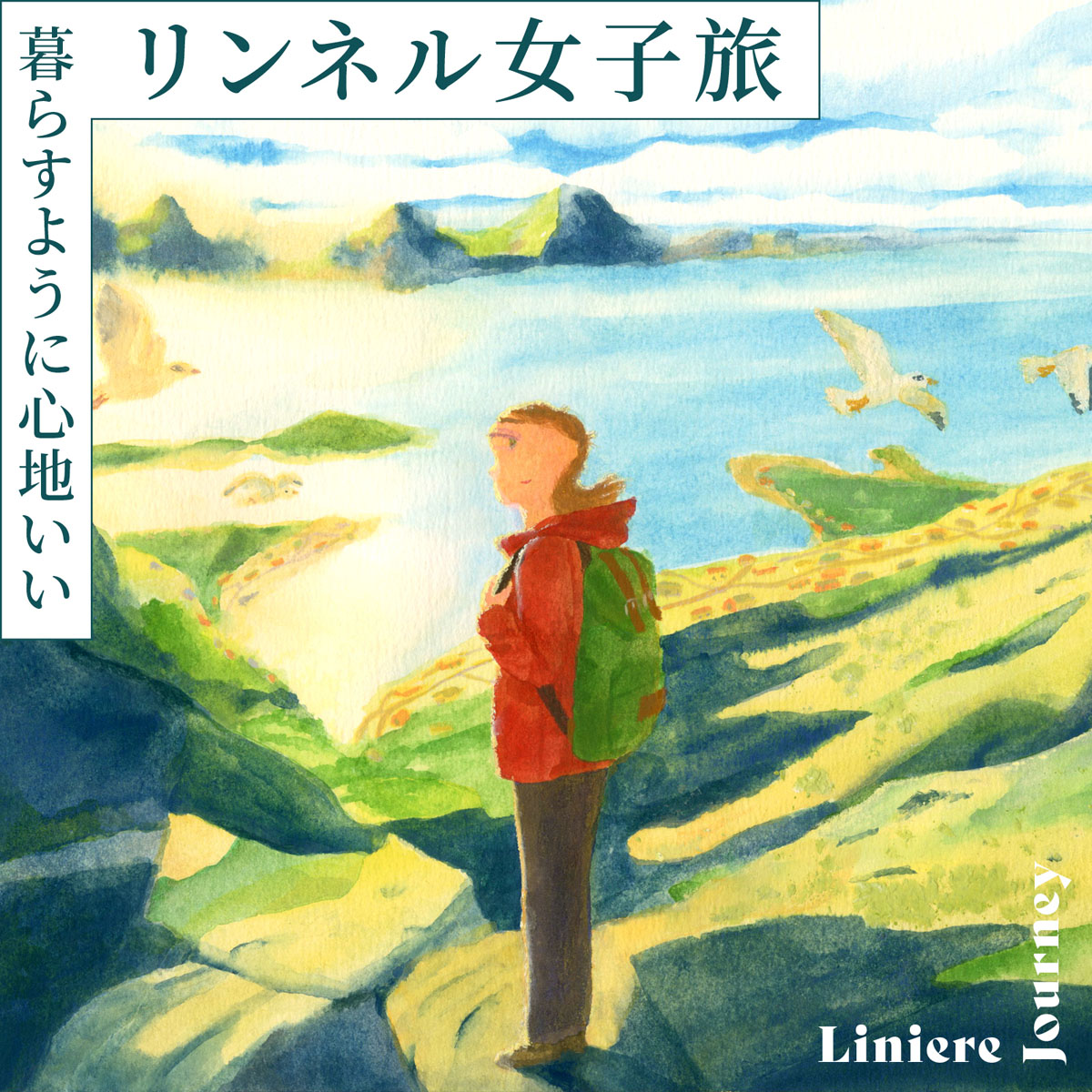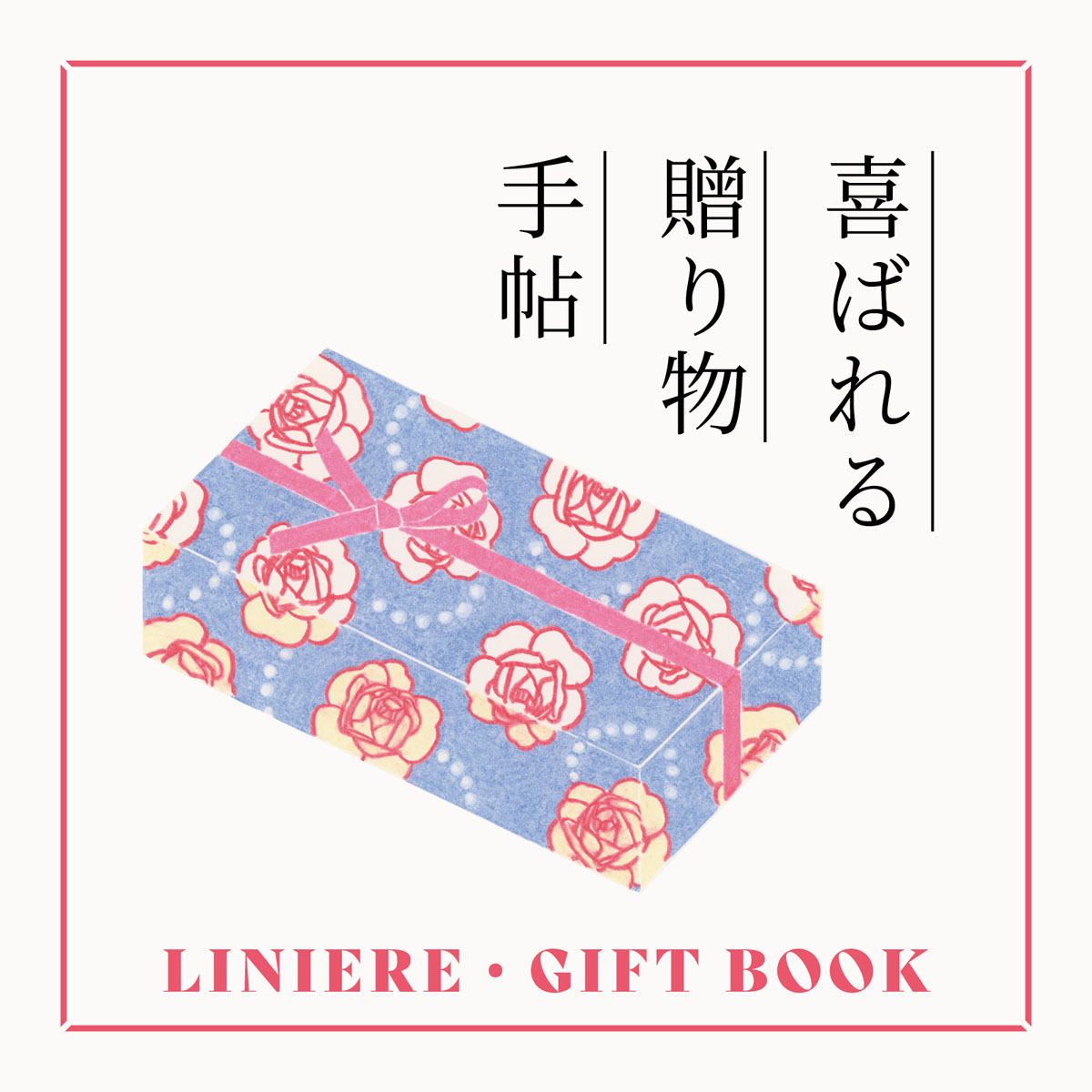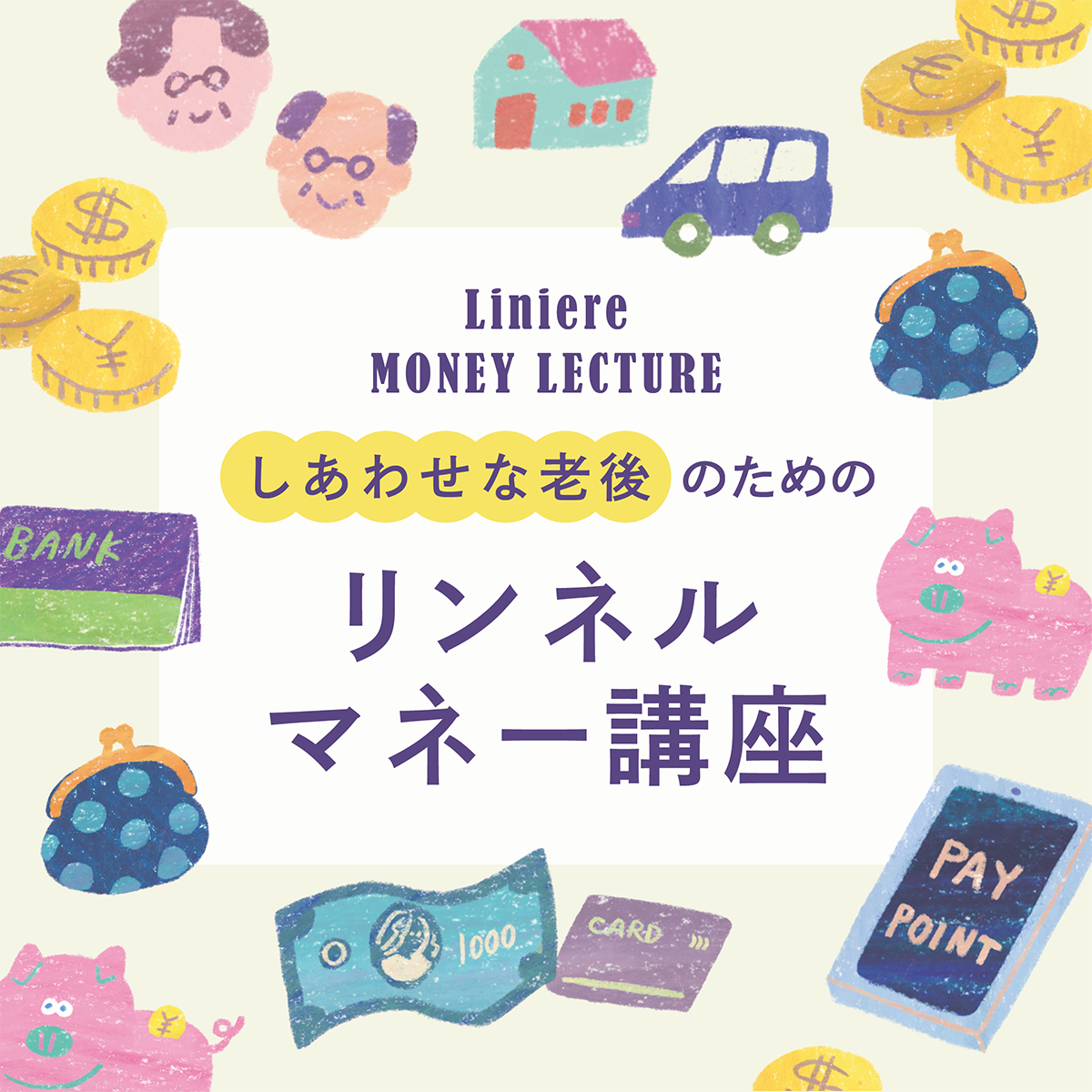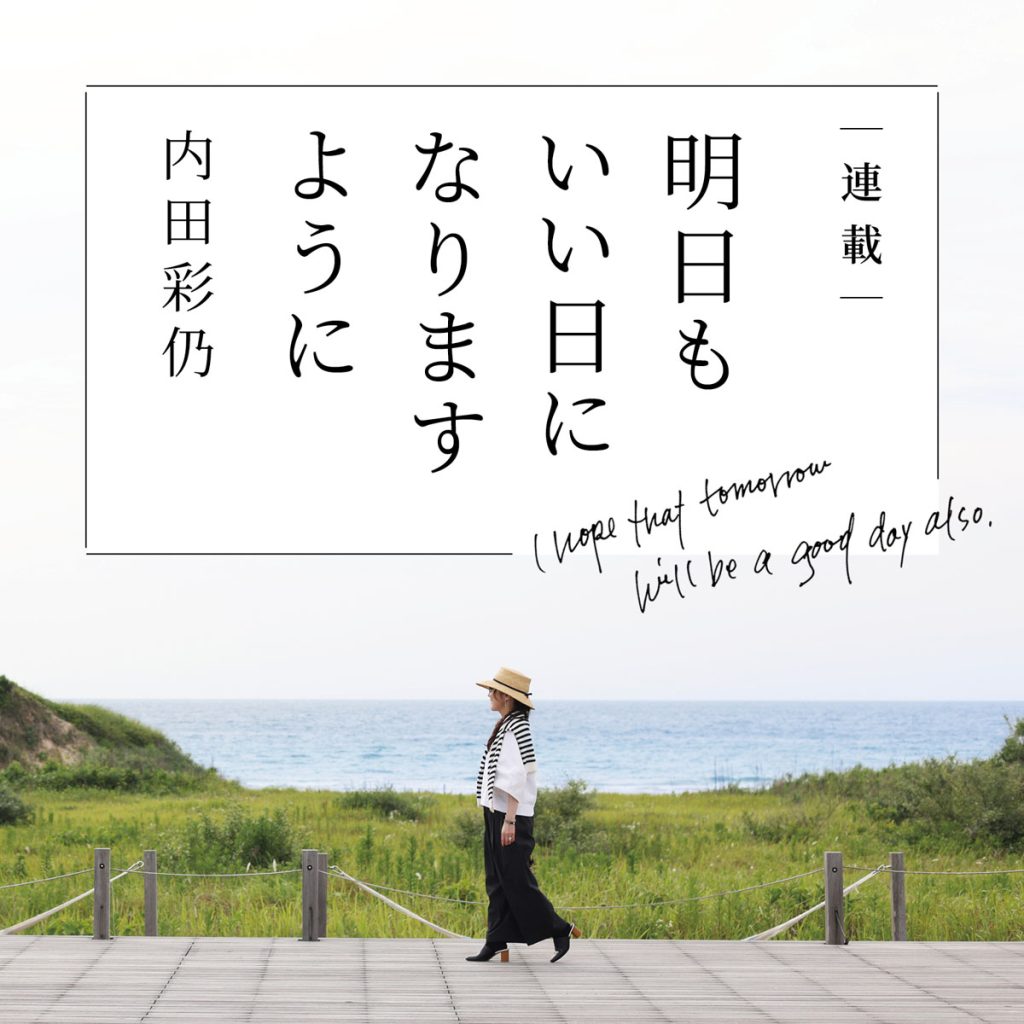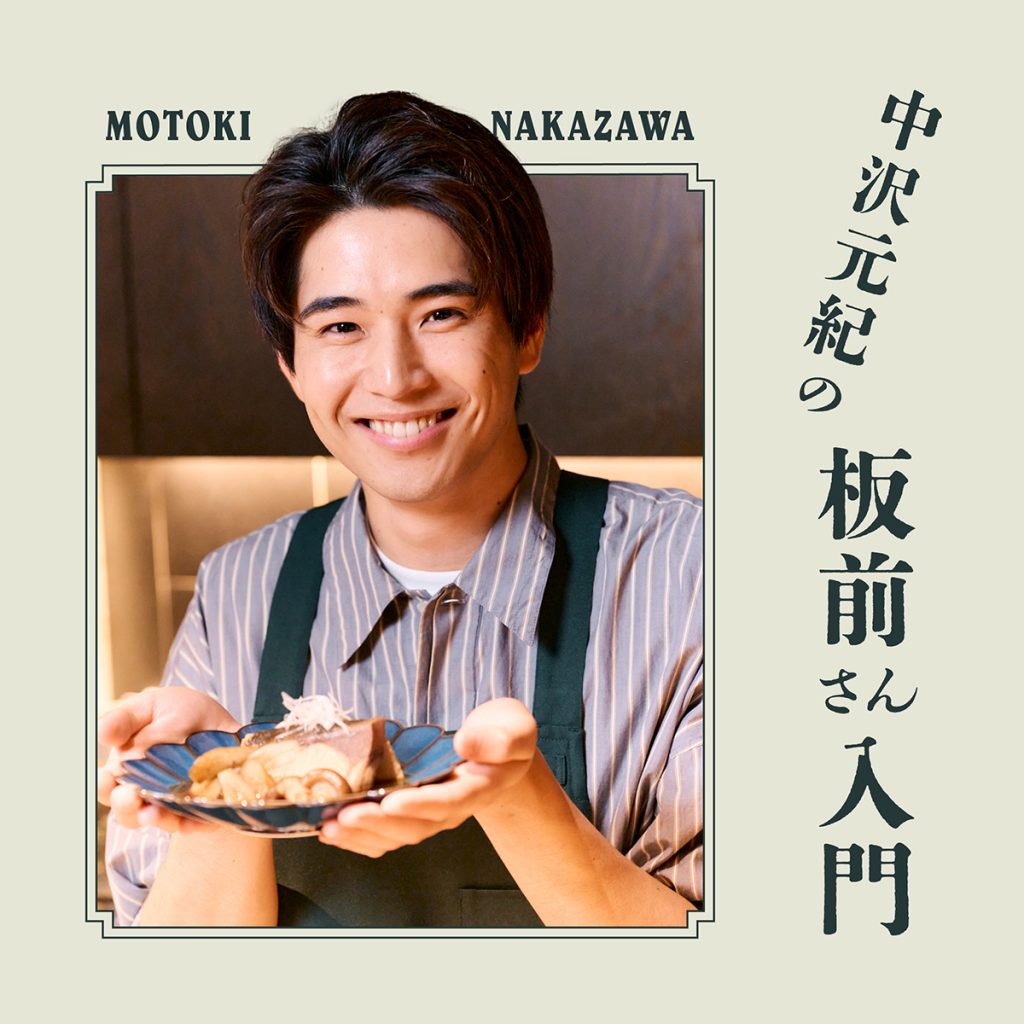LIFESTYLE
:妊娠出産・育児でもらえるお金が、実はこんなに! いくらもらえる?条件は? 知らないと損!: 「社労士が解説②」【マネー講座】
LIFESTYLE
:

子どもを生み、育てることは、人生の喜びであるとともに、大きなお金が必要になることでもあります。少しでも安心して子育てができるよう、サポートしてくれる出産育児一時金や育休や児童手当などの給付金や助成金制度について、社会保険労務士(社労士)が解説します。
教えてくれたのは…
出産、育児で休んだときにもらえるお金
出産・育児で仕事を休んでいる間の生活を支援するための手当金。2025年4月からは、パパとママが一緒に育休を取る場合の給付金が新設されるなど、サポートが広がっています。
①出産手当金

<出産手当金で支給される金額>
標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の2/3。
(例)
標準報酬日額7000円で、産休期間が98日の場合
7000円×2/3×98日=45万7333円支給される
②育児休業給付金
雇用保険の被保険者が、1歳未満の子どもを育てるために育休を取得したときに支給されるもの。男女問わず、対象となります。
給付を受けるためには以下の条件を満たすことが必要になります。
・産後休前の2年間の就労日数が11日以上ある月が12カ月以上ある
・育休中に賃金が支払われていた場合は、その金額が1カ月あたり休業前の8割未満
・育休期間中に就業している日数が、1カ月あたり10日(80時間)以下
<育児休業給付金で支給される金額>
育児休業開始日から180日目まで:標準報酬日額の67%
育児休業開始日から181日目以降:標準報酬日額の50%
(例)
標準報酬日額7000円で、子どもが1歳になるまで休んだ場合
育休開始から180日目まで:7000円×0.67×180日=84万4200円
育休開始から181日目~300日目まで:7000円×0.5×120日=42万円
③出生時育児休業給付金
★2025年4月新設
男性の育児休業の取得を促すために、新たに創設された給付金制度。子どもが生まれてから一定期間内に、両親とも14日以上28日以内の育児休業を取得した場合に支給されるもの。休業開始前の賃金の13%相当額が支給され、前述の「育児休業給付金」と合わせると、給付率が最大80%に。手取り額のほぼ100%がサポートされる計算になります。
対象期間は、男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内です。育児休業を1回4週間(28日)以内で、2回に分けて取得した場合は分割で受け取ることも可能。
<出生時育児休業給付金で支給される金額>
休業開始時の賃金日額×67%×休業期間の日数分
④育児時短就業給付金
★2025年4月新設
2歳未満の子どもの養育のため、時短勤務をすることで給料が減ってしまうのをカバーする目的で、新しく創設された制度。時短後に支給される賃金と給付金の合計額が時短前の賃金を超えないように給付率を調整する仕組みとなっており、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を上限に給付金が支給されます。
<育児時短就業で支給される金額>
時短勤務中に支払われた賃金日額×10%×時短勤務日数分
出産、育児にかかる費用を補助するお金
出産や育児にかかるお金の負担を軽くするための手当金。
現状の「児童手当」も、この10月から子どもの対象年齢が延長されるなど、給付対象が手厚くなってきています。
①出産育児一時金

<出産育児一時金で支給される金額>
子ども1人につき50万円
②児童手当
★2024年10月から変更
子どもの養育にかかるお金をサポートするための制度。子ども1人あたり月額1万円(3歳未満は月額1万5000円)。2024年10月(2024年12月支給分)からは、対象となる子どもの年齢が18歳(高校卒業)までに延長、親の所得制限も撤廃されます。さらに、第3子以降は支給額が月額3万円に増額されます。
子どもが生まれたら、出生日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に申請が必要です。また、他の市区町村から転入したとき、転入先の市区町村での手続きが必要です(公務員の場合は、勤務先に申請)。
<児童手当で支給される金額>
子ども1人につき 月1万円 (3歳未満は月1万5000円)
※第3子以降は、1人あたり月3万円
③保育料無償化
2019年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する、3~5歳までのすべての子どもの利用料が無償化されました(幼稚園については、月額2万5700円までが無償に)。無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間。子ども・子育て支援制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市区町村によって償還払いの手続きが必要な場合もあります。
ひとり親家庭を支援するお金
離婚や死別、未婚での出産などによって、1人で18歳(障害のある子どもは20歳)までの子どもを育てているひとり親家庭をサポートする制度(父子家庭も対象)。
①児童扶養手当
ひとり親家庭で、所得制限などの条件を満たしている場合、「児童手当」と同時に、「児童扶養手当」を受給できます。もらえる金額は所得や保護者の状況によって異なりますが、全額支給の場合で、子ども1人目は月額4万5500円が支給され、子ども2人目は月額1万750円を加算。この11月からは子ども3人目以降も1人あたり、月額1万750円が加算されることになりました。
②ひとり親家族等医療費助成制度
ひとり親やその子ども、または両親がいない子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部を住んでいる市区町村が助成する制度。
ひとり親家庭で、18歳(障害のある子どもは20歳)までの子どもがいて、健康保険に加入している場合が支給対象です。基本的に保険診療の範囲内での治療であれば自己負担額の全額(※)が助成されます。また、各自治体で定める所得制限額を超えている場合や、生活保護を受けている場合は、支給対象外となります。
この他にも、各自治体で「ひとり親家庭の子育て支援」に関する助成制度を設けているところが多く、例えば、家賃補助や水道料金の一部減免などの支援制度がああります。住んでいる自治体のホームページ等で確認しましょう。
※助成金額は、入院、通院などの条件によって異なります
>>こちらもチェック
リポートした人 Profile
マネーライター みとも はやみ
編集プロダクション、出版社の勤務を経て、2011年よりフリーランスで活動。
20年以上、生活情報誌を中心に家計やりくりにまつわる記事の編集・取材・執筆に携わる。これまでに取材した実例は、延べ1000件以上。
Illustration:Naoko Horikawa text & web edit:Hayami Mitomo
※写真・イラスト・文章の無断転載はご遠慮ください
※このページで掲載している情報は、2024年10月15日現在のものです
おすすめ記事 RELATED ARTICLES
Recommend

 SNAPRanking
SNAPRanking
DAILY
/
WEEKLY