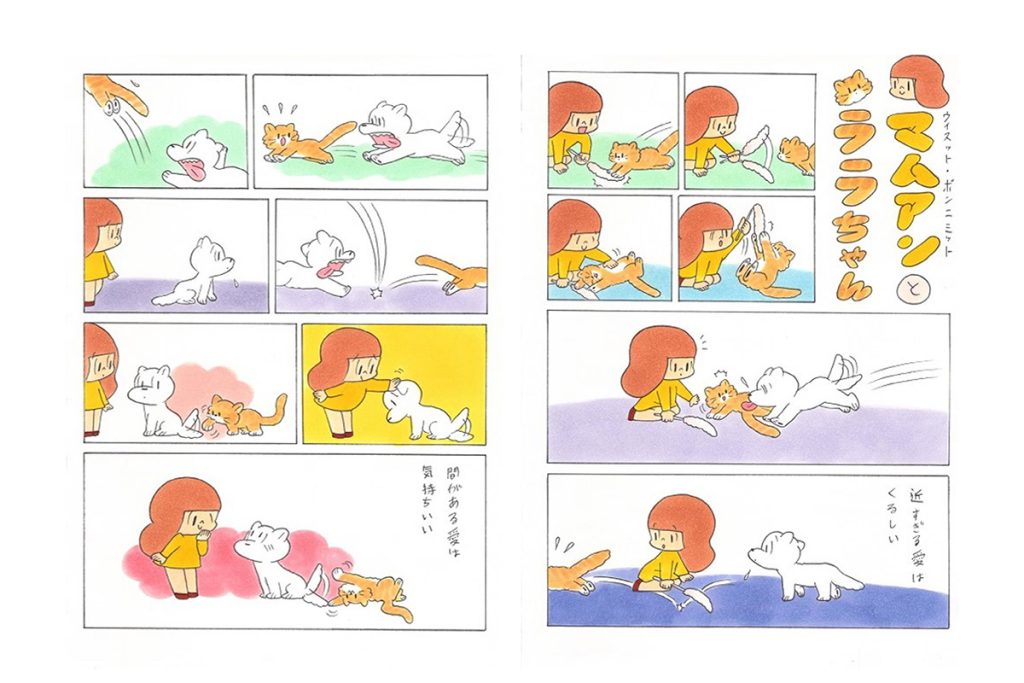CULTURE
:環境に流されず幸せをつかむためには? 大女優・高峰秀子さんの養女で『ふたり』の著者、斎藤明美さんが語る誇り高き女優の人生
CULTURE
:

2024年に生誕100年を迎えた、日本映画史に残る偉大な女優、高峰秀子さん。55歳で引退するまで400本近くの作品に出演し、随筆家としても26作の著書を遺しました。晩年に養女となり、近くでその姿を見てきた文筆家の斎藤明美さんが、このたび『ふたり ~救われた女と救った男』(扶桑社)を上梓。高峰さんの恵まれなかった生い立ちや夫・松山善三さんとの出会い、高峰さんとの思い出など、たっぷりお話を伺いました。

おもしろくてかっこいい。斎藤さんだから知る高峰さんの素顔
仕事を通して知り合い、10年ほど親交を深めたのち、高峰さんと夫で脚本家・映画監督の松山善三さんの養女となったという斎藤さん。高峰さんの最後の15年ほどを一緒に過ごしたといいます。
「その頃はとっくに女優を辞めていましたが、主婦って大変だなと思いました。死ぬ間際まで、毎日ごはんを作っていてすごいなと。私が初めてこの家に来たとき、“使っているんですか?”と聞いたくらい、キッチンはピカピカ。整頓のコツを聞くと、“いつ死んでもいいように”っていうんです。高峰は自分でも几帳面を通り越して『癇性(かんしょう)』だというくらい、清潔好きでした。冷蔵庫の中も輪じみひとつない。調味料やごまなども全部同じ、透明のタッパーに入れ替えて使っていましたね。
センスがすごく良くて、キッチンはドイツ製のものを船便で運ばせたそうですが、松山が『鍋女』と呼ぶくらい、引き出しの中には鍋がいっぱい。普通ならどこに何があるか忘れてしまいそうですが、そういうことが一切なく、全部頭に入っている。探し物や忘れ物をしたのを一度も見たことがないくらい、ついうっかりということがない人。準備万端ぶりはすごかったです」
60代後半から家具や洋服、食器、骨董、絵画とあらゆるものを処分し、70代半ばで筆を折り、人との付き合いを断って生活をしていたという高峰さん。
「洋服はほぼ黒かグレーで、原色のものはなかったです。派手なものを嫌い、紫の小さなミヤコワスレが一番好きな花でした。花は毎日欠かさず生けていて、トルコキキョウや小菊、フリージア、庭に咲く水仙や白椿を小さい焼き物に一輪だけ飾るということをしていましたね。好き嫌いがものすごく激しくて、変わっているんですよ。私も変わっているらしいので、高峰ほどいろいろな知識はなかったけど、感じるものがすごく似ていたと思います。だから高峰が好きそうなもの、嫌いなものが自然とわかるんですよ。
引退後もたくさん来ていた仕事の話をすべて断っていたけど、相手が二の句が告げないくらい愛想もなくて。私はそれをかっこよくておもしろいと思っていました。どう思われても構わないようなところがあったから、誤解されても言い訳もしない。お金やもの、地位も、高峰は何も欲しくない人だったから、足もとを見られない。だからかっこいいんです。
私は喜怒哀楽がはっきりしていてわかりやすく、高峰が初めてくれた手紙に“あなたほど直情的な人はしりません”と書いてあったのですが、後に高峰はそれほどまっすぐじゃない人ばかりに囲まれていたんだとわかりました。養女と言われたときはさすがにびっくりしましたが、“あなたのことは全部わかってます”と言われて、尊敬する人にそう言われたことは嬉しかったですね」
恵まれない環境、望まない仕事から救ってくれた松山さんとの出会い

晩年も一緒に外出するときは、高峰さんが夫の松山さんの服をコーディネートしていたそう。
華々しい映画スターという仕事が実は嫌いで、1日も早く辞めたかったという高峰さん。
「高峰は母親が亡くなった後、5歳で父親の妹の養女になり、養母と親戚20人近くを養うため、金銭製造機のごとく働かされていました。親の愛情もなく、自分が好きじゃない職業で、小学校も1ヶ月しか行けなかった。それを救ったのが松山。高峰は松山じゃないと幸せになれなかったと思います。
中学生の頃に高峰のファンだった松山は、助監督として映画『カルメン故郷に帰る』で初めて仕事を共にしましたが、身分が違いすぎて、高峰は松山の顔さえ覚えていない状態。だけど、その少し後に松山は高峰に交際を申し込むんです。雲の上の人に普通は言えないですよ、でもその申し込みを高峰は受けるんですよね。井上靖さんがいった、『事実は小説よりも奇なり』ってその通りだなと思います。高峰は骨董を見る目もありましたが、人間を見る目があったんです」
当初は、釣り合わないといわれていた2人の結婚。マスコミの記者が、続いたとしても3年だと賭けをしたくらいだったそう。
「高峰は自分で美人ではないし、馬鹿だと思っていたんです。私はあれだけ頭のいい人には会ったことがないですが、謙虚で自分を過小評価していました。松山を選んだのは誠実だから。こんな人には二度と会えないと思ったって、当時のインタビューで語っています。高峰は松山が考えているような難しいことはわからないから、1日に1回は楽しいことをいって笑ってもらうことを心がけているといっていました。あんなに美人の奥さんが家にいて、料理もものすごくおいしくて楽しいって、松山もどれだけ幸せだったかと思います。
結婚したとき松山は貧乏だったので、奥さんを引退させるべく500本脚本を書くなど、ものすごい仕事をしました。2人の収入がちょうど交差したのが50歳くらい。5歳から50年働き、55歳で引退しました。女優の仕事になんの未練もなかったんです。そして死が2人を分かつまで添い遂げた。だから、本当に幸せだったと思いますよ」
高峰さんの本を通して、伝えたいこと

名文家としても知られた高峰さん。『おいしい人間』(扶桑社文庫)は、最近復刻された一冊。
今回刊行された『ふたり』をはじめ、高峰さんの本の復刻にも尽力されている斎藤さん。
「生誕100年ということで、これだけ本を出すことを高峰は喜んでいないと思います。ただ私はそんな高峰の気持ちはわかっているけど、客観的に見てやる価値のある人だと思うからやっています。高峰は忘れてほしい、煙のように消えていきたいと望んでいた人。でも日本映画というものがなくならない限り、忘れないでと言わなくても忘れられない人だと思っています。
彼女にもし欲があれば、もっと映画に出ているし、ドラマだって出たかもしれないし、本だってもっと書いていたと思います。でも彼女は書くことも演じることも、自分から望んだことは一度もなかった。自分から望んだのはとうちゃん(松山さん)との結婚だけ。普通の生活がしたかっただけの人なんです」
高峰さんには上昇志向ではなく向上心があり、自慢ではなく自負があったと話す斎藤さん。本書を通して伝えたいことは?
「高峰の人生はオセロゲームに例えると、5歳のときにはすでにほぼ黒。負けが決まりの状態からスタートしたのですが、1枚だけ握りしめた白いコマで一個一個ひっくり返していくんです。忍耐強く諦めず、人生を投げず。そして私が出会った70歳の頃には、全面を白くした。環境や親とか社会のせいにせず、自分の理想と希望を捨てないで、”私はこんな人間になりたい”と諦めずに努力して目指していたら、必ず幸せになれると感じてほしいです。高峰はそれを実証した人だったから。
人生の勝ち負けは、自分が望む人生かどうか。何か目標を持ち、今の状態がもし嫌なら、何が嫌なのか、不満なのか、自分と向き合って考えてほしいです。高峰が持っていた一枚の白いコマとはなんだったのか。もっと言えば、あなたにとってこれだけは離したくない、人にも譲らず、死ぬまで握りしめていたい一枚の白いコマとはなんなのか、それを考えてほしいなと思います」
こちらもチェック!
text & edit:Mayumi Akagi
※画像・文章の無断転載はご遠慮ください
おすすめ記事 RELATED ARTICLES
Recommend

 SNAPRanking
SNAPRanking
DAILY
/
WEEKLY