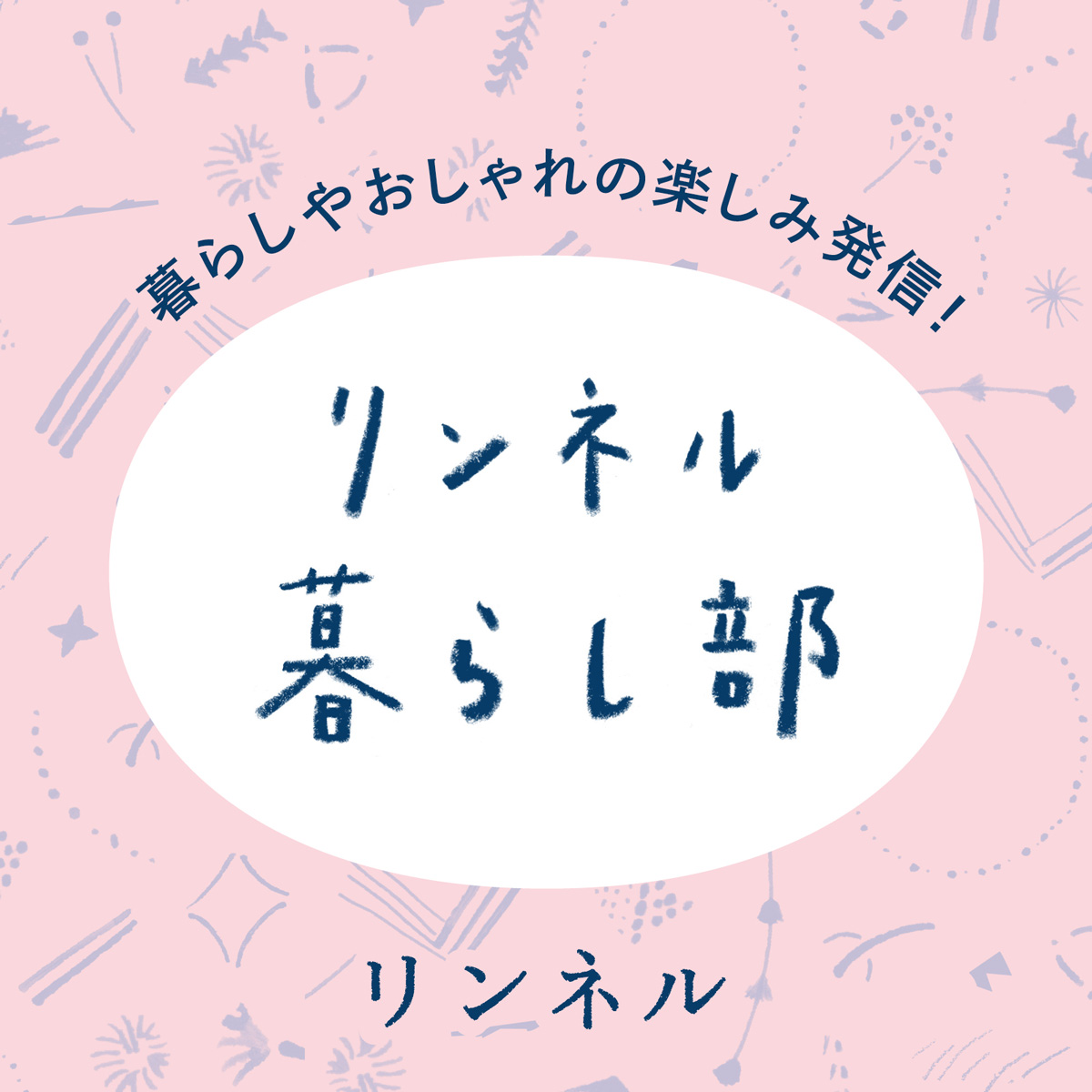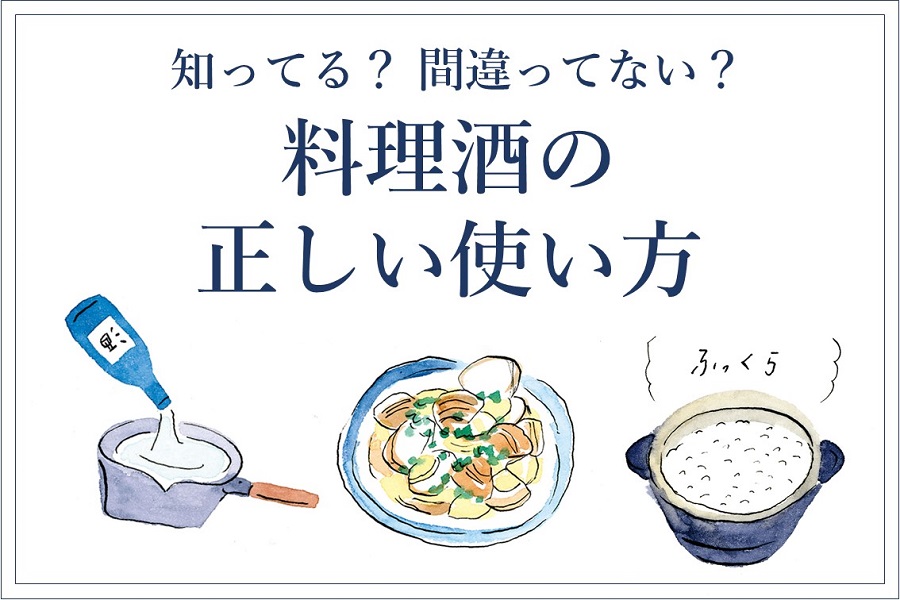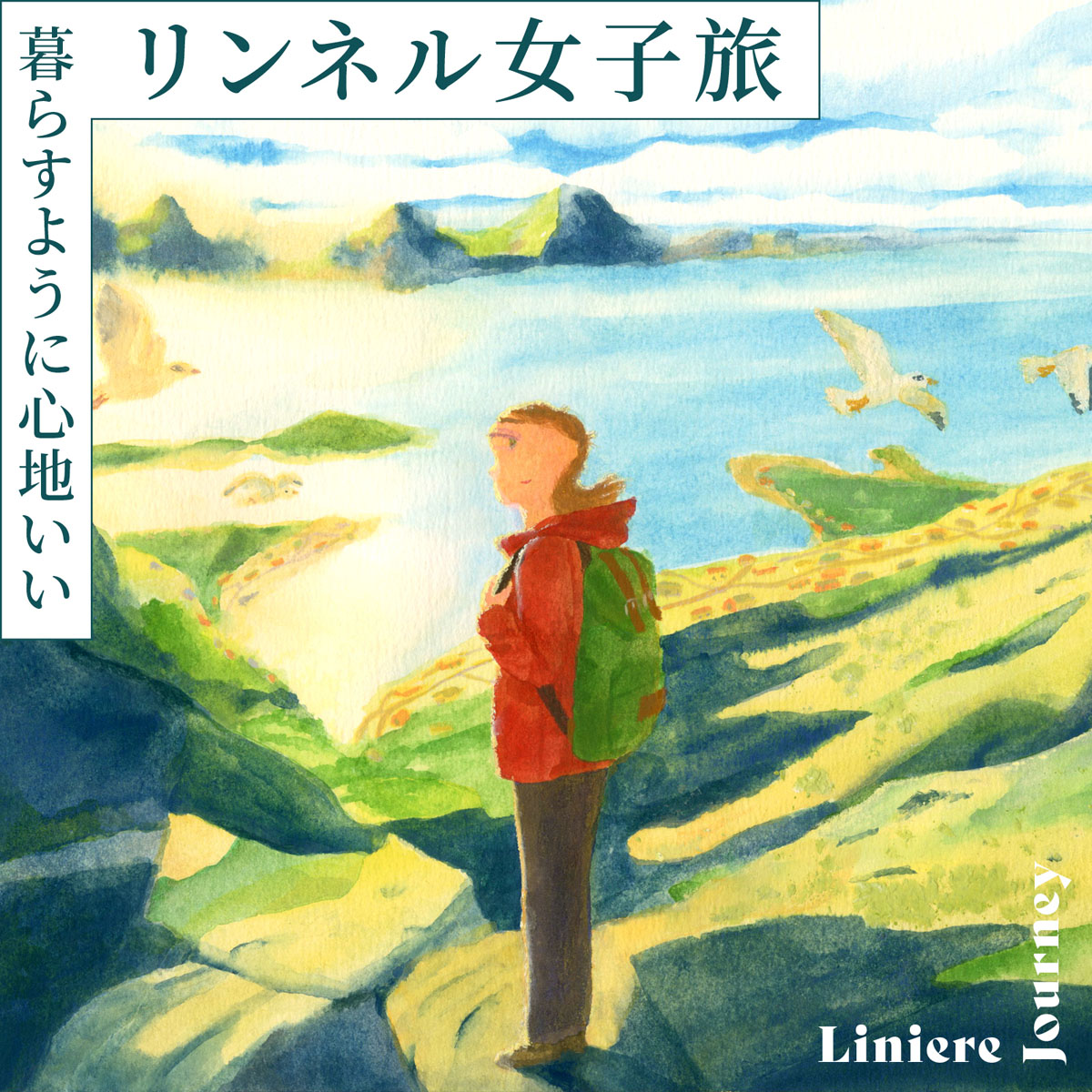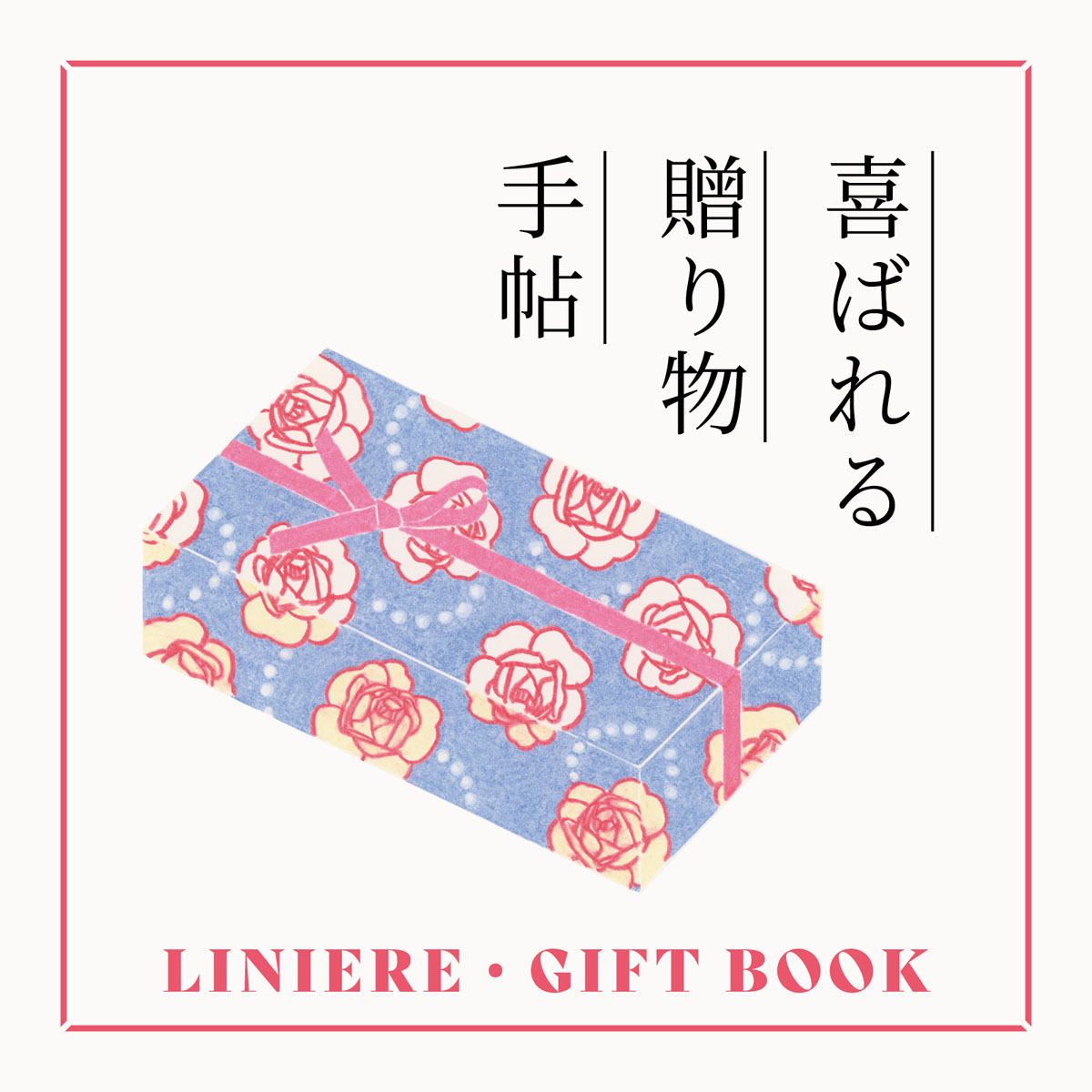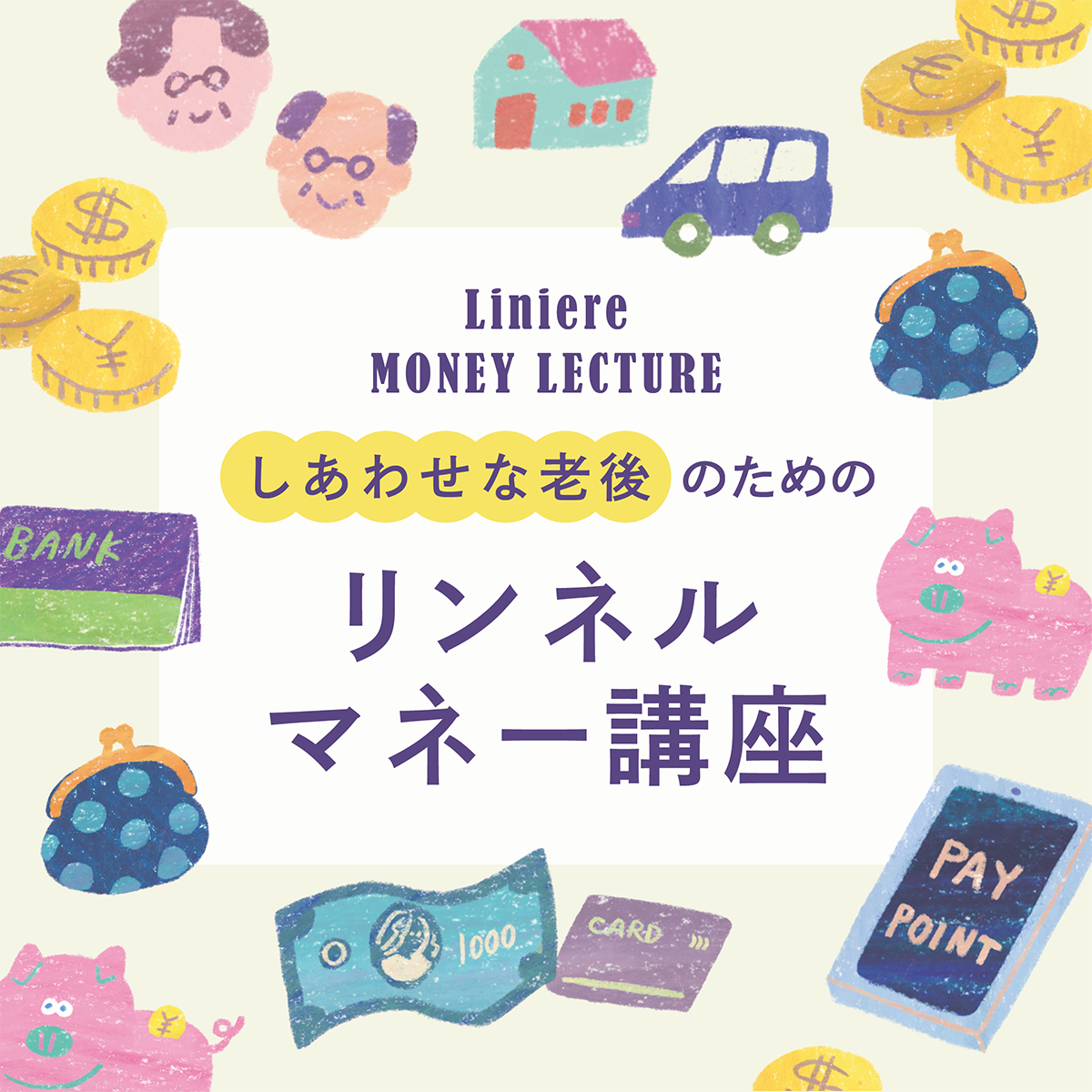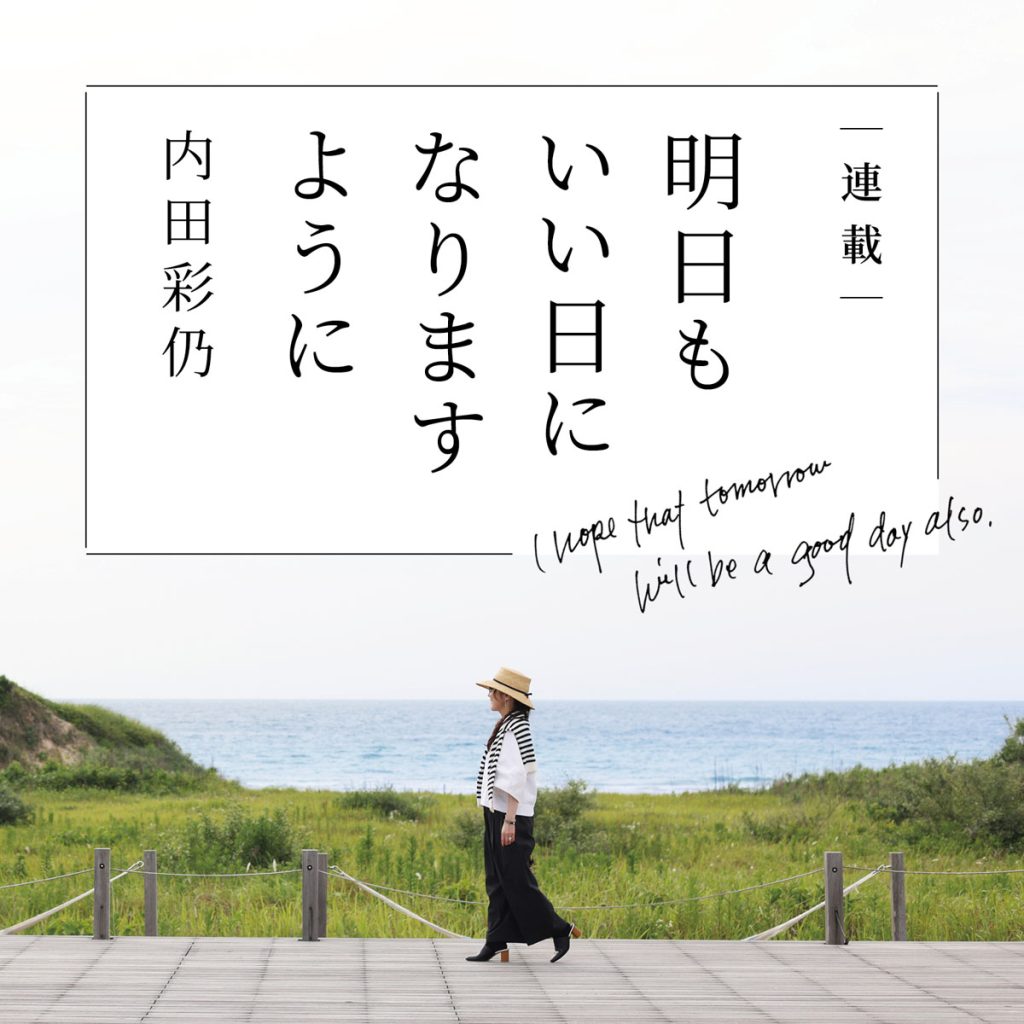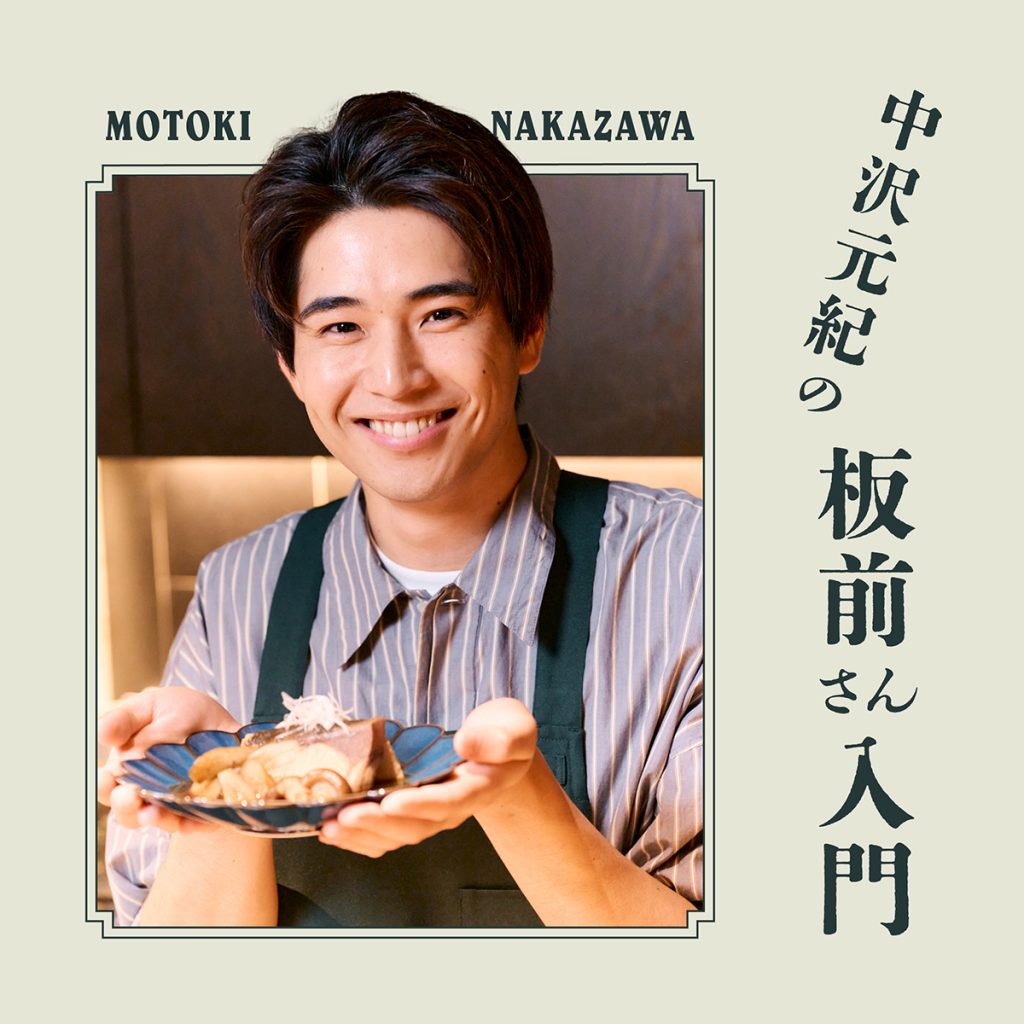FOOD
:「みりん」の正しい使い方をおさらい:甘みづけだけじゃない効果的な活用法とは?
FOOD
:

「みりんは甘みづけ」だけの調味料だと思っていたらもったいない! 効果を最大限に引き出すみりんの正しい使い方を、料理家の松田美智子さんに教えていただきました。
「みりん」の正しい使い方をおさらい:甘みづけだけじゃない効果的な活用法とは?
改めて知りたい「みりん」のこと
<主原料(本みりん)>
もち米、米麹、焼酎またはアルコール
<製法>
40〜60日かけて糖化・熟成させる。もち米のデンプンやタンパク質が糖類やアミノ酸に分解されて複雑に絡み合い、独特の風味が生まれる。
<3つの種類>
本みりん:もち米、米麹、焼酎またはアルコールから作られる。アルコール分は14%程度。
みりん風調味料:糖類や酸味料、調味料などを加えた、みりんに似せた甘味料。アルコール分は1%未満。
発酵調味料:もち米、米麹、アルコールを原料に発酵やブレンドし、2%の食塩を加え、飲めなくさせたもの。アルコール分は14%程度。
参考/全国味醂協会「本みりんの知識」
<保存方法>
開封後すぐに使いきらない場合は、基本的に冷蔵保存を
みりんの選び方
酒の一種であるみりんの効果が得られるのは、本みりん。みりん風調味料は、アルコール度数1%未満で、本みりんとは原料も製法も違う甘味料。発酵調味料は塩分を含むので注意が必要。
本みりんの効果を活かした使い方のコツ
・上品な甘みとうまみをつける
・深いコクを出す
・照りを出す
・塩や酢のカドをとる
・煮崩れを防ぐ
アルコール分を含み、酒と同じくうまみがありますが、みりんは各種の糖類やアミノ酸が含まれ、上品でまろやかな甘みもあわせ持ちます。そのため、塩や酢のカドをとる効果も。また、各種の糖類が美しい照りに。そして、アルコールと糖類の作用で、煮崩れを防ぐ効果も。
ポイントは、料理の始めや最後に加えること
上品な甘みをつけたいときは、砂糖と同じように酒を加えたすぐあとに加えて。料理の始めのほうに加えることで、調理中に本みりんのアルコール分を飛ばすこともできます。また、みりんの糖類は、アルコールに反応すると煮崩れしにくくなるという効果も。かぼちゃやいも類など、やわらかい野菜をゆっくりと煮含めるときには最初から加えましょう。また、最後に加えてひと煮立ちさせると料理の味をまろやかにしたり、照り・ツヤをきれいに出せます。
みりんで料理のお悩み解決! こんなとき、みりんがあれば
【お悩み】砂糖を使うと甘くなりすぎる
↓
砂糖の代わりにみりんを使う

【お悩み】そうめんなのに、めんつゆがない!
↓
みりんを使って自家製めんつゆを作成

さらに、「煮切りみりん」があると便利!
「煮切りみりん」とは、みりんを加熱し、アルコール分をあらかじめ飛ばしたもの。アルコールの匂いがなくなるまで煮詰めて作ります。
加熱しない料理や時短調理の味方に!
使い方1:さっと煮の仕上げに
じっくり煮含めるのもおいしいけれど、夏はさっとさわやかに煮たいときも多いはず。煮切りみりんを仕上げにひと回しするだけで、コクやほのかな甘みが加わり、味がまとまります。

酢の味がたち過ぎて、酢のものの味がまとまらない、という悩みには、煮切りみりんを。米酢に少量加えると、酸味のカドがとれて、食べやすくなります。

煮切り酒(鍋に入れた酒を温めて、蒸発したアルコール分に火をつけて燃やしたもの)と合わせると、加熱調理しないレシピの幅が広がります。たとえば、しょうゆに煮切り酒と煮切りみりんを合わせ、刺身を漬けておくだけで、品のいい味の漬け丼が完成!
教えていただいた
松田美智子さん profile

llustration:Kayo Yamaguchi text:Kaori Akiyama web edit:Riho Abe
リンネル2018年9月号より
※画像・イラスト・文章の無断転載はご遠慮ください
おすすめ記事 RELATED ARTICLES
Recommend

 SNAPRanking
SNAPRanking
DAILY
/
WEEKLY