HEALTH
:【秋バテ不調を整えましょう】 頭痛や肩こり、食欲不振…夏→秋に出やすい症状ってどんなもの?
HEALTH
:

猛暑の日々が終わり、少しずつ過ごしやすくなる季節の変わり目に、頭痛や肩こり、眠気、食欲不振などの症状を感じたら“秋バテ”のサインかも! 夏疲れのダメージを蓄積したまま次の季節を迎えると、体の不調サイクルはエンドレスに。今回は秋バテを防ぐ習慣について国際中医薬膳師・瀬戸佳子先生に伺いました。
教えてくれたのは…瀬戸佳子先生

暦のリズムに合わせて
夏→秋の不調をケア
年々暑さが厳しくなる夏。暦の上では秋に入ったといっても、夏バテが夏疲れとして残り、そのまま秋バテになってしまうといいます。

体感や気温だけでなく、暦を意識したケアが不調の予防につながります。
「温暖化で暑さが長引くようになったとはいえ、日照時間に大きな変化はありません。立秋を迎える8月7日ごろから徐々に日の入りが早くなり、秋の虫が鳴き始めます。暑いからとエアコンや冷たいものを取り続けていると内臓に冷えが蓄積し、胃腸機能の低下へとつながります。胃腸の弱りから体力不足になることも秋バテのひとつの要因です」

季節が進むことで体のダメージが出やすい箇所も変わってくるそう。
「東洋医学には五臓という概念があり、季節の流れと連動していると考えられています。夏は心臓や血管と関わりの強い血液や水分を巡らせる臓器に疲れが出やすく、秋は喉や鼻などの呼吸器や皮膚、大腸などがウィークポイント。夏疲れをしっかり整えつつ、秋の弱点もケアしていくことで、だるさや疲れやすさなどの不調の悪循環を断ち切るきっかけを作りましょう」

こちらもチェック!
illustration:Naomi Mori edit & text:Hiroko Ishiwata
リンネル2024年11月号より
※画像・文章の無断転載はご遠慮ください
おすすめ記事 RELATED ARTICLES
Recommend

 SNAPRanking
SNAPRanking
DAILY
/
WEEKLY











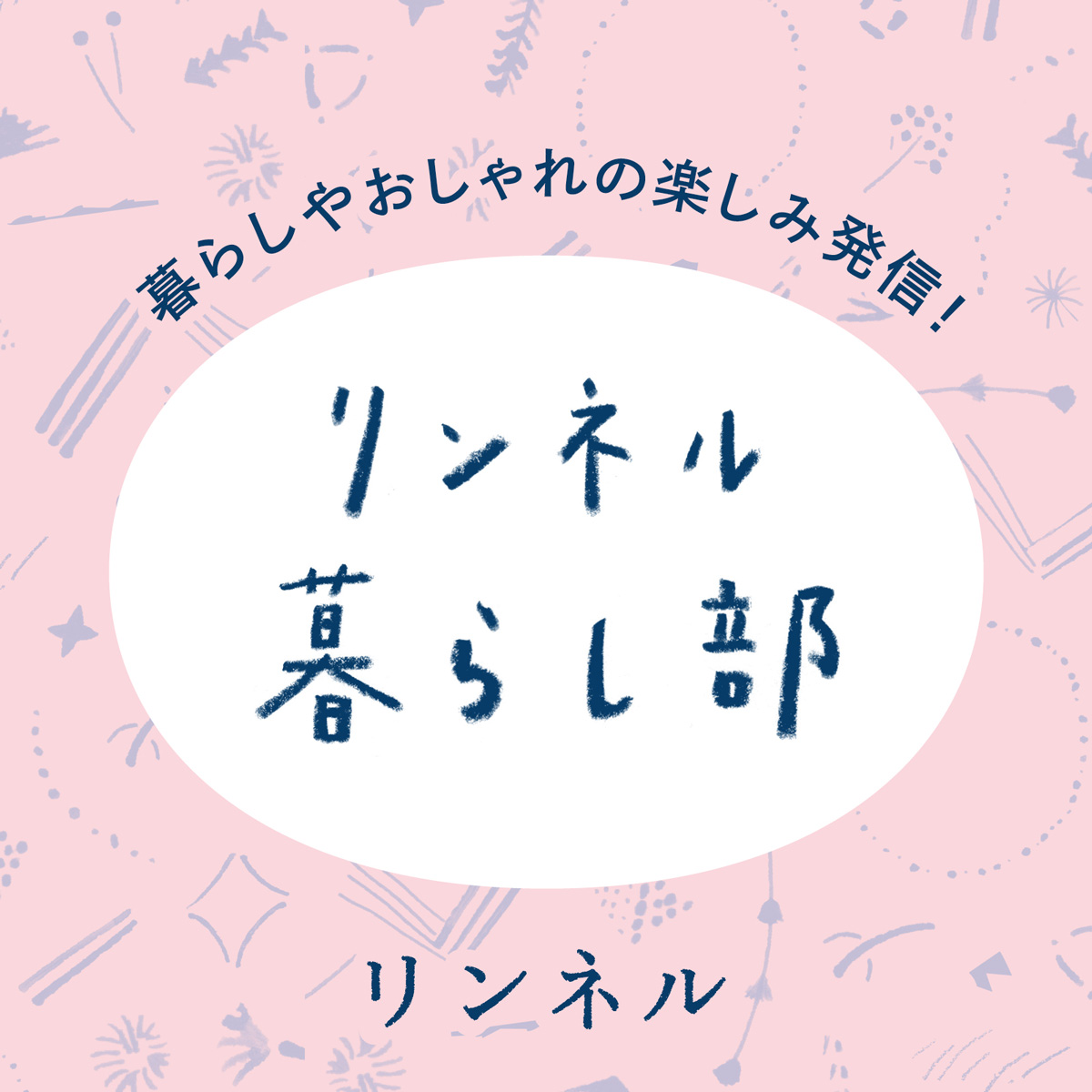












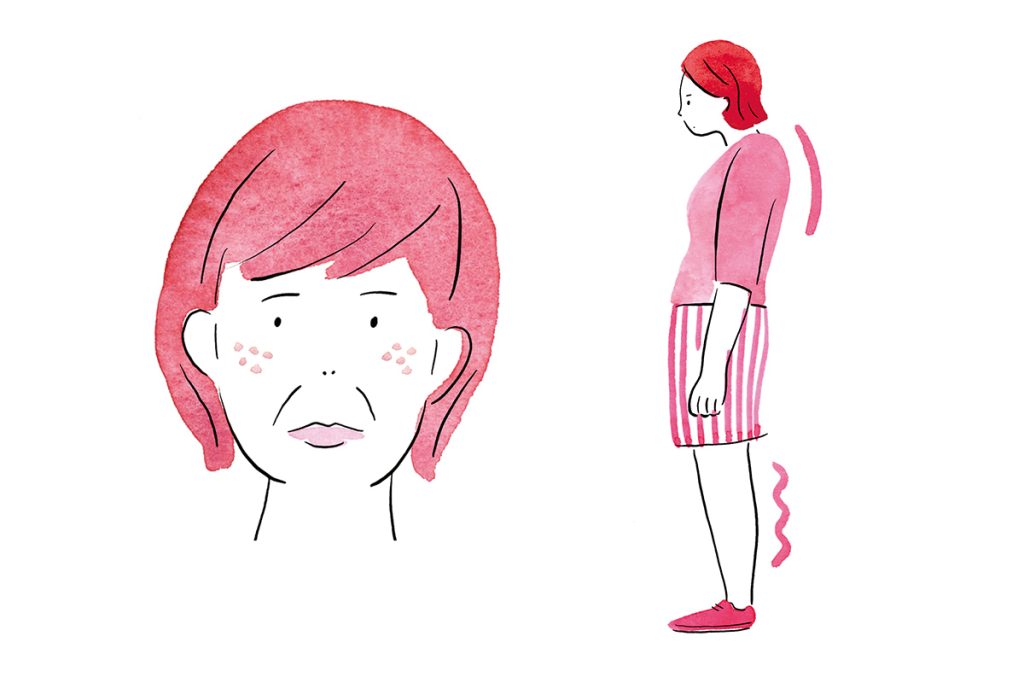

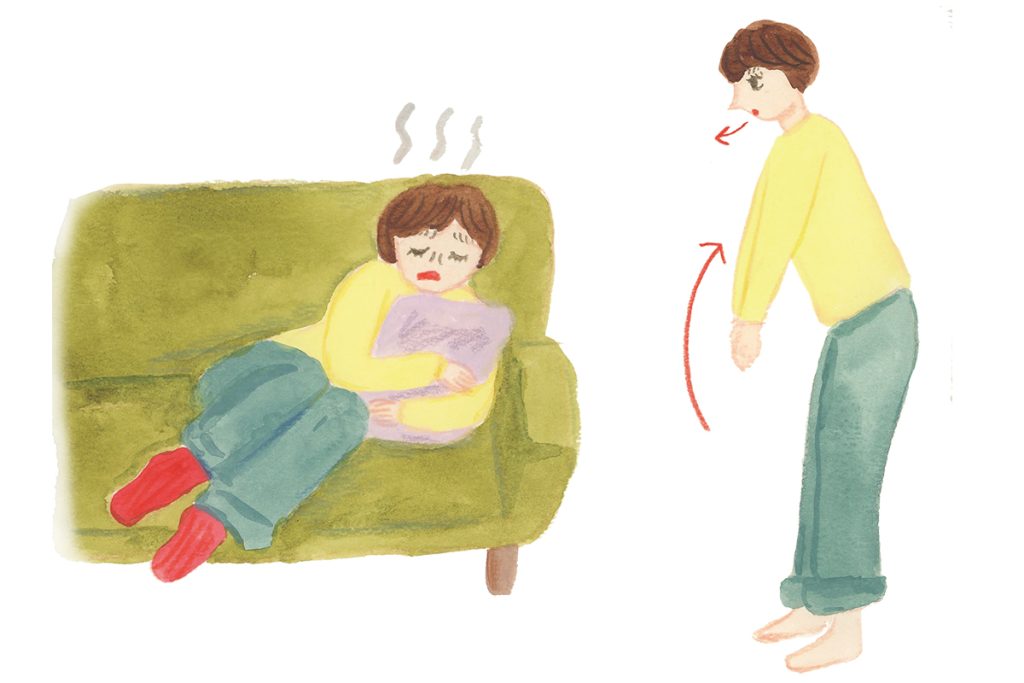













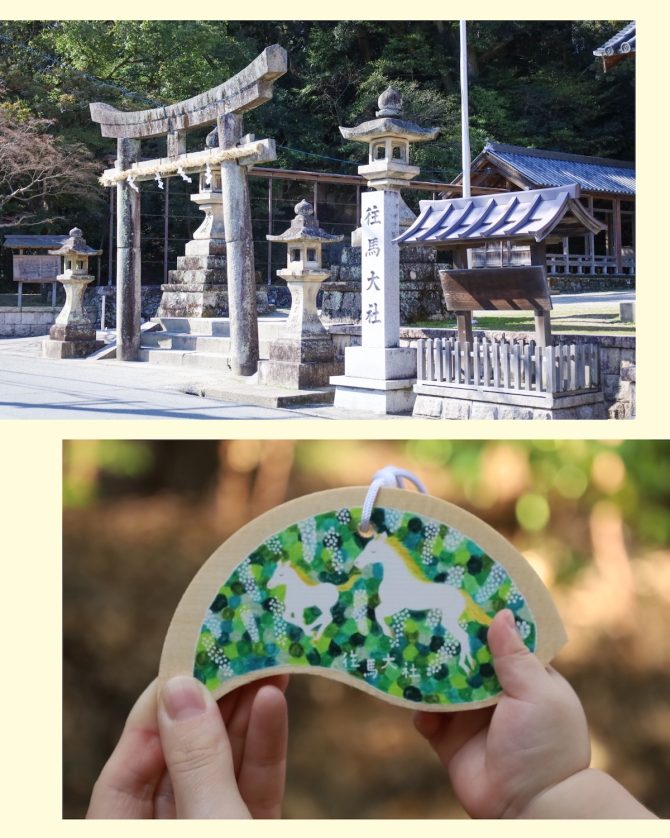













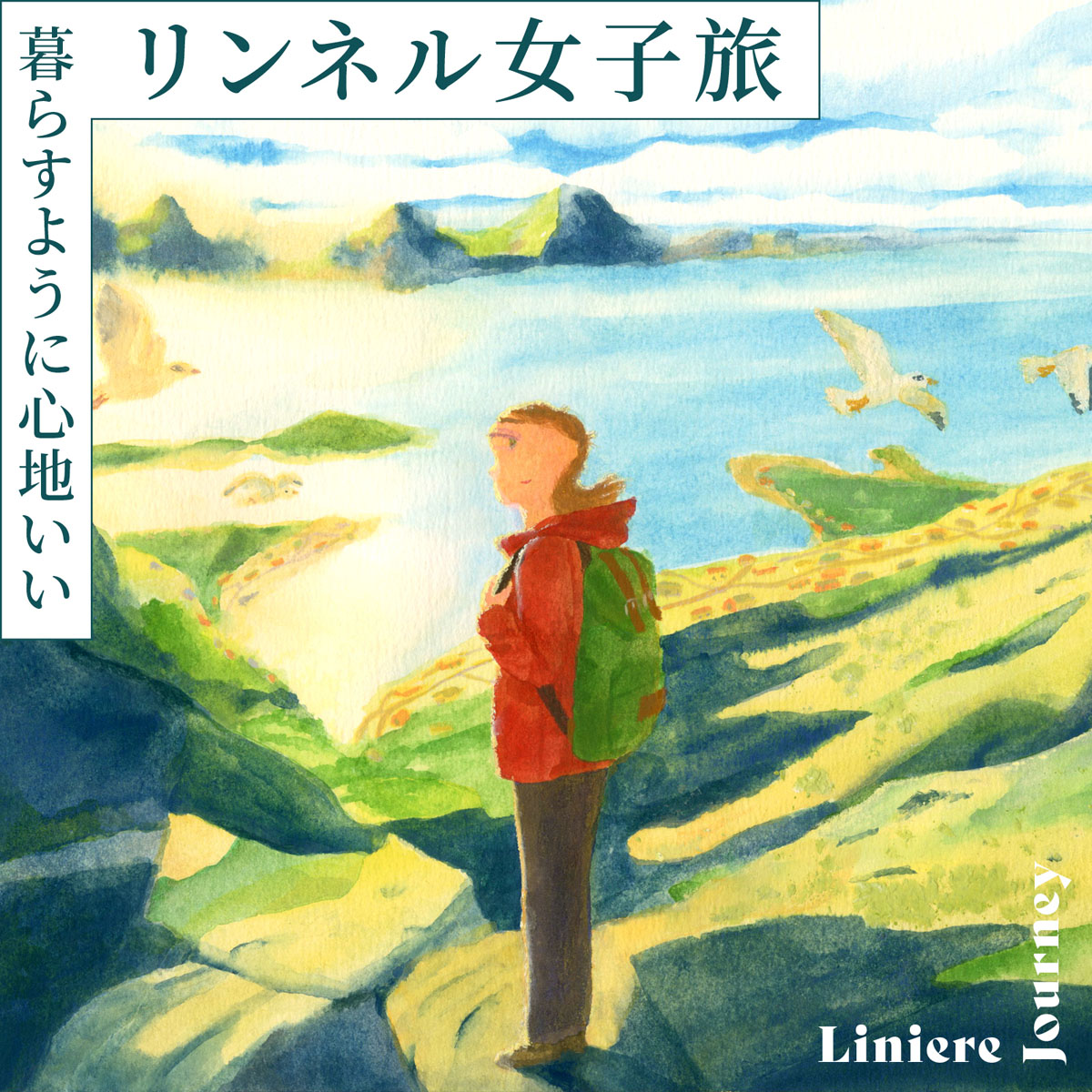
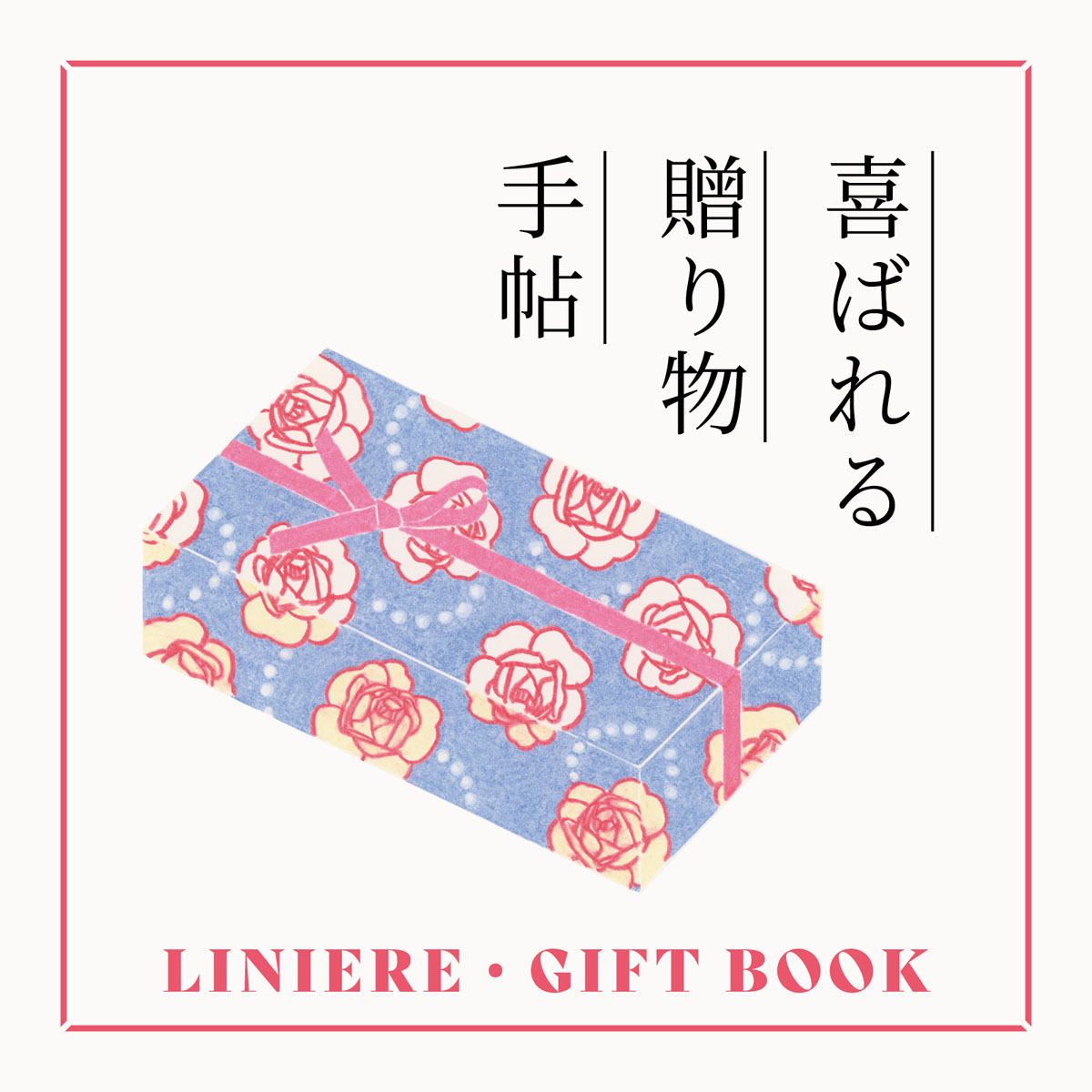

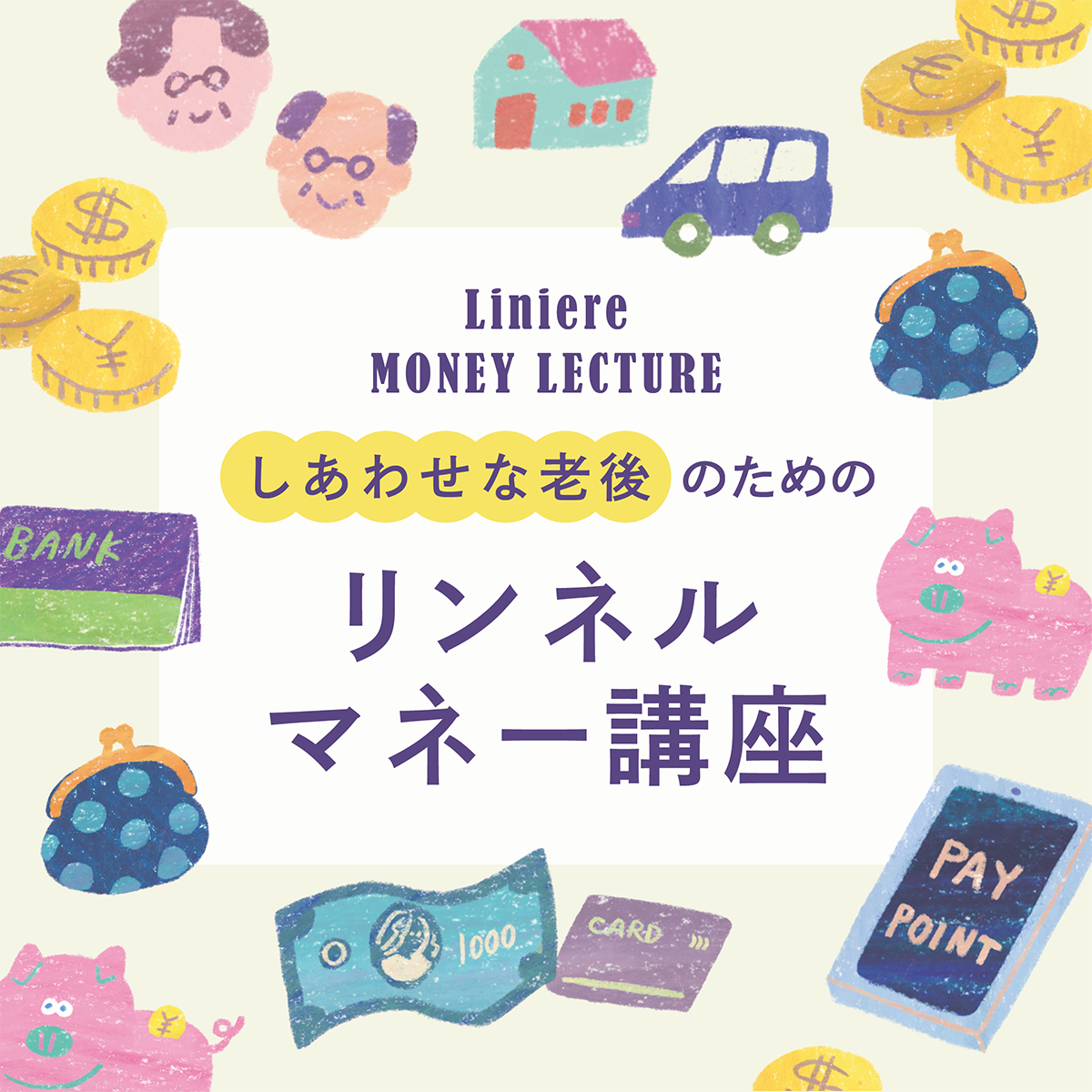
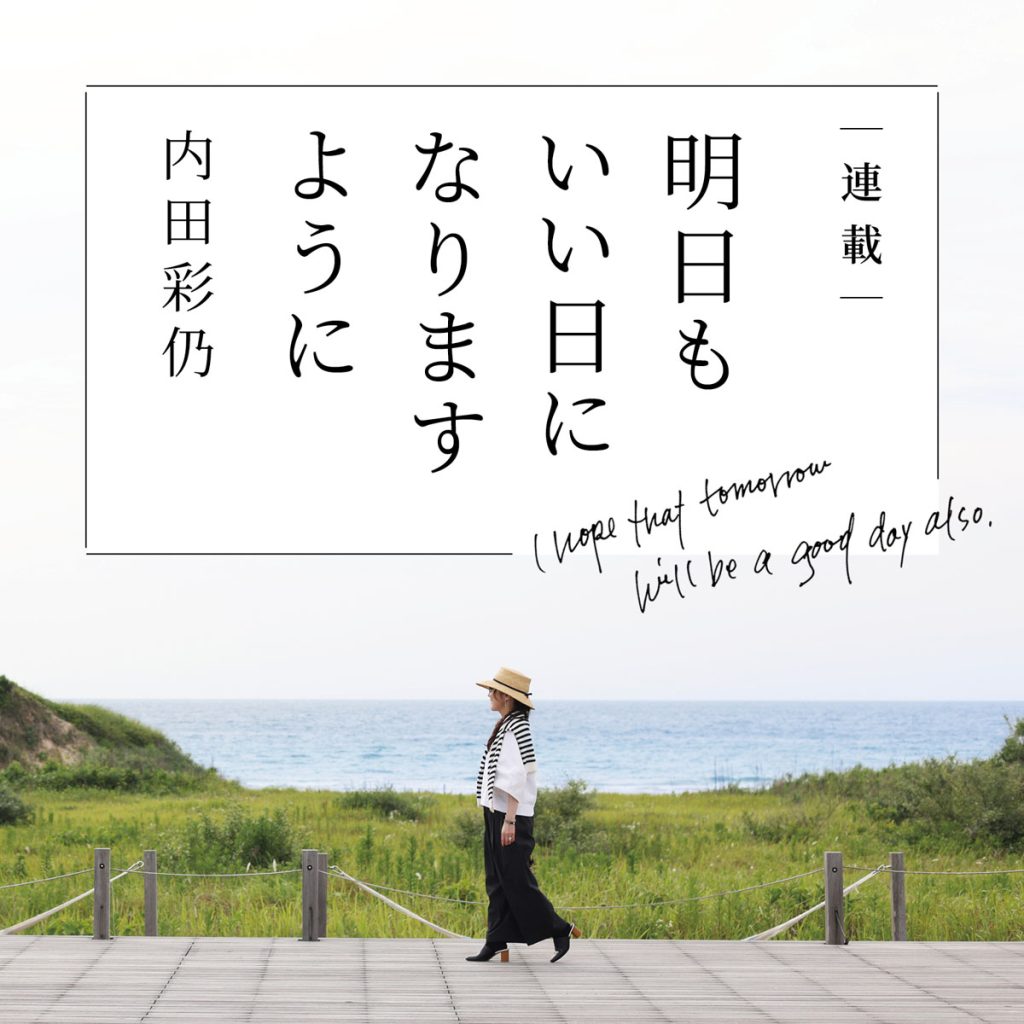
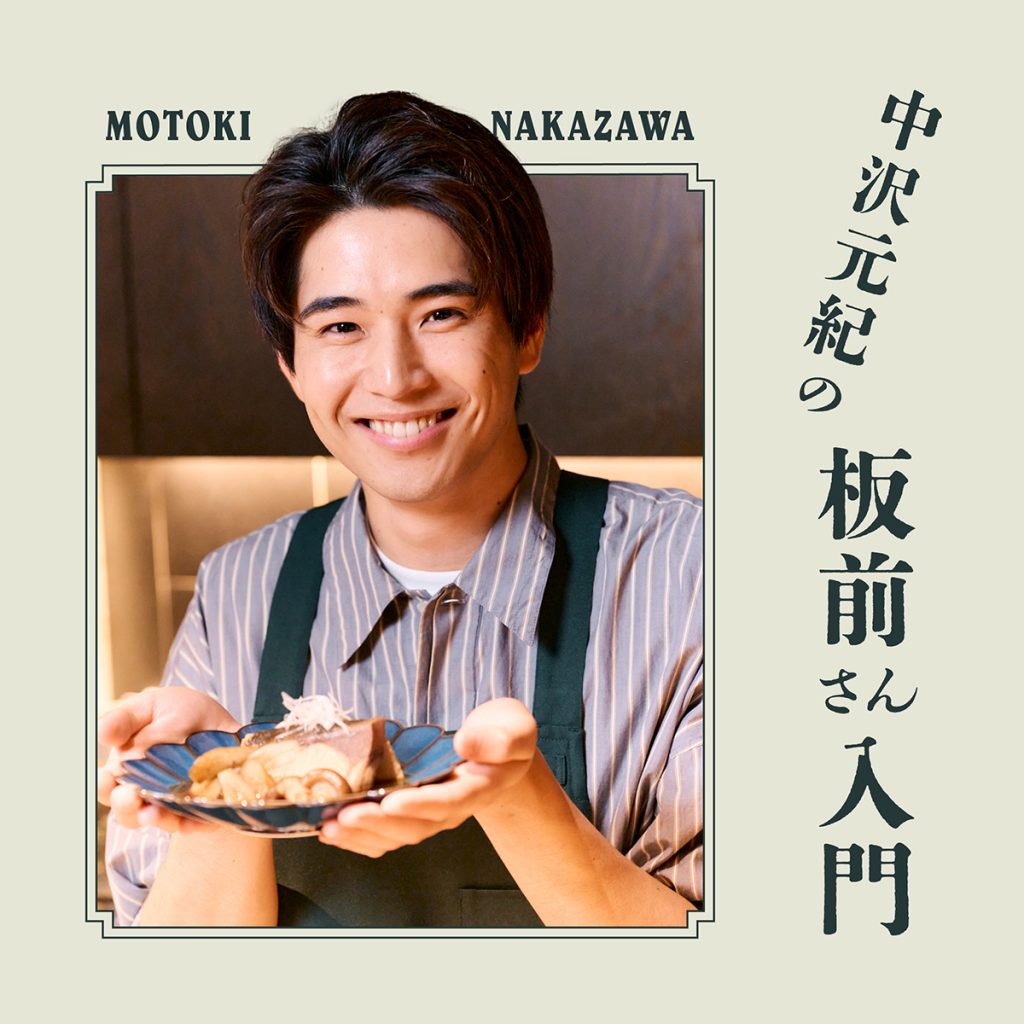








「今まで夏バテをしなかった人もダウンしてしまうほど、今は夏のインパクトが強くなってきています。その大きなダメージをそのままにしておくと、しわ寄せがくるのは、次の季節の秋。東洋医学の養よう生じょうでは、その季節の過ごし方が次の季節の体調不良に関係していると考えます。夏疲れをしっかりケアしないと、秋、冬、さらに通年の不調や病のもとにつながる恐れがあります」